2011年10月07日
■壮絶な人生!ジョブズの世界を変えた信念とは?
昨日のブログで続き、続きを書くとのことだったのですが、ジョブズの訃報に
追悼の意を込めて今日はジョブズのストーリーに変更したいと思います。
ぜひ知らなかった方は、読んで下さい。
スティーブ・ジョブズとは?
スティーブ・ウォズニアックと共に、
ワンボードマイコン「Apple I」を開発・販売し、アップル社設立後には、パーソナルコンピュータ「Apple II」を発表。株式公開後には2億ドルもの巨額を手中にし、20代でフォーブスの長者番付に載り、世間の注目を集めた。
ゼロックス社パロアルト研究所を見学した際、Altoで動作していた暫定Dynabook環境のグラフィカルユーザインターフェースにインスピレーションを受け、パーソナルコンピュータ「Lisa」を開発。
続いて、ジェフ・ラスキンらのMacintoshプロジェクトの主導権を握り、新たなコンピュータ像を創造した。発表された「Macintosh」は、当時存在したあらゆるパソコンを凌駕する洗練されたものであり、再び時の人となった。
しかし、本人の立ち居振舞いのために社内を混乱させたとされ、アップルの役員達から社内でのすべての職を剥奪された。
アップル退職後、ルーカスフィルムのコンピュータ・アニメーション部門を買収して、ピクサー・アニメーション・スタジオを設立。
また、自ら創立したNeXT Computerで、ワークステーション「NeXTcube」と先進的オペレーティングシステム (OS) NEXTSTEPを開発した。1996年、業績不振に陥っていたアップル社にNeXTを売却することで復帰、1997年には、暫定CEOとなる。
その後、ライバルとされていたマイクロソフトとの資本連携に踏み切り、Macintosh互換機へのライセンスを停止、社内のリストラを進めてアップル社の業績を回復させた。
2000年、正式にCEOに就任。2001年から2003年にかけてMacintoshのOSをNeXTの技術を基盤としたMac OS Xへと切り替える。その後はiPod・iPhone・iPadといった一連の製品群を軸に、アップル社の業務範囲を従来のパソコンからデジタル家電とメディア配信事業へと拡大させた。
暫定CEOに就任して以来、基本給与として、年1ドルしか受け取っていなかったことで有名であり(実質的には無給与であるが、この1ドルという額は居住地の州法により、社会保障を受けるために給与証明が必要なことによる)、
このため「世界で最も給与の安いCEO」とも呼ばれた。2006年に、ピクサーをディズニーが買収したことにより、ディズニーの個人筆頭株主となり、同社の役員に就任したが、ディズニーからの役員報酬は辞退していた。
2011年10月5日、アップルはジョブズが死去したと発表した。別の報道では死因は膵癌と報道している。享年57(満56歳)。
有名な話がある。
ある部下が、スティーブ・ジョブズ氏から、日曜日に突然電話がかかってきました。ジョブズ氏が何かに怒り、電話をするのは平日ならお馴染みのことだったのですが、日曜にまで電話がかかってくるなんてことは、普通じゃありえなかったそうです。
当然、ビクビクしながら電話をとようですが、ジョブズ氏の電話内容はこういったものでした。
「iPhoneでGoogleのロゴを見ているのだけど、アイコンが気に食わない。Googleのロゴの二つ目のOの黄色のグラデーションがおかしいんだ。とにかく間違っていて、明日修正してくれるかな?」
という内容だったようです。
これだけ大企業のトップが、色のグラデーションまで気を使う、そのことに驚きました。
その話を聞いてから、ジョブズのファンに、本を読みあさりました。
彼はモノづくりにこだわり、徹底してスタイリッシュでクールであり続けることに
こだわったのです。
背面のデザインについての、この名言も彼の生き様を物語っています。
「もし君が家具のデザイナーでとても美しい箪笥を作っていたら、背面で誰も見ないからと言って後ろにベニヤ板をはったりするだろうか。背面でもそこに存在すると感じれば、後ろにも美しい木材を使うだろう。それは、夜よく眠るために、本物の証のために、品質のために。全てが一貫された出来映えのために、きっとそうするだろう。」
最前線で働く彼らにさえ、厳しい問題がたくさんあって、簡単には解決できません。苦しんで苦しんで精一杯やる。自分を信じてとにかくやる。ジョブズ氏と共通しているのは、
お金じゃない、儲けじゃない、世界を変えるんだ!という情熱から生まれるイノベーションです。
大きなビジョンがあるからこそ、全力で走り抜けることが出来る。全力だから、細部にもこだわる。一度きりの人生、そうありたいと強く思わされました。
そして彼は本当に世界を変えてしまったのです。
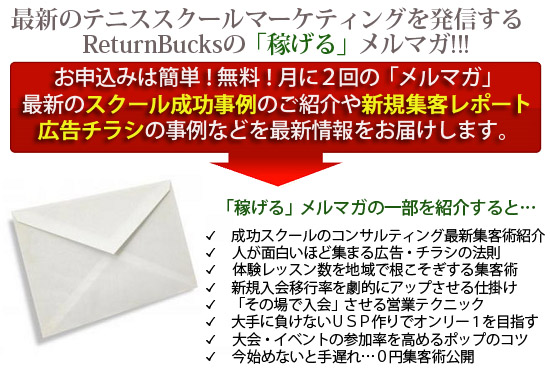
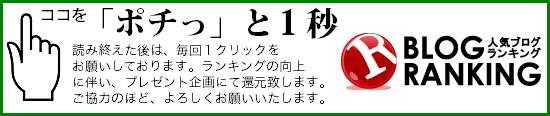
追悼の意を込めて今日はジョブズのストーリーに変更したいと思います。
ぜひ知らなかった方は、読んで下さい。
スティーブ・ジョブズとは?
20代で2億ドル(日本円で約15,6億)をかせぐ
スティーブ・ウォズニアックと共に、
ワンボードマイコン「Apple I」を開発・販売し、アップル社設立後には、パーソナルコンピュータ「Apple II」を発表。株式公開後には2億ドルもの巨額を手中にし、20代でフォーブスの長者番付に載り、世間の注目を集めた。
ゼロックス社パロアルト研究所を見学した際、Altoで動作していた暫定Dynabook環境のグラフィカルユーザインターフェースにインスピレーションを受け、パーソナルコンピュータ「Lisa」を開発。
こだわり抜いた「ディティール」
続いて、ジェフ・ラスキンらのMacintoshプロジェクトの主導権を握り、新たなコンピュータ像を創造した。発表された「Macintosh」は、当時存在したあらゆるパソコンを凌駕する洗練されたものであり、再び時の人となった。
しかし、奈落の底からの生還
しかし、本人の立ち居振舞いのために社内を混乱させたとされ、アップルの役員達から社内でのすべての職を剥奪された。
アップル退職後、ルーカスフィルムのコンピュータ・アニメーション部門を買収して、ピクサー・アニメーション・スタジオを設立。
また、自ら創立したNeXT Computerで、ワークステーション「NeXTcube」と先進的オペレーティングシステム (OS) NEXTSTEPを開発した。1996年、業績不振に陥っていたアップル社にNeXTを売却することで復帰、1997年には、暫定CEOとなる。
その後、ライバルとされていたマイクロソフトとの資本連携に踏み切り、Macintosh互換機へのライセンスを停止、社内のリストラを進めてアップル社の業績を回復させた。
復活。そして象徴へ
2000年、正式にCEOに就任。2001年から2003年にかけてMacintoshのOSをNeXTの技術を基盤としたMac OS Xへと切り替える。その後はiPod・iPhone・iPadといった一連の製品群を軸に、アップル社の業務範囲を従来のパソコンからデジタル家電とメディア配信事業へと拡大させた。
暫定CEOに就任して以来、基本給与として、年1ドルしか受け取っていなかったことで有名であり(実質的には無給与であるが、この1ドルという額は居住地の州法により、社会保障を受けるために給与証明が必要なことによる)、
このため「世界で最も給与の安いCEO」とも呼ばれた。2006年に、ピクサーをディズニーが買収したことにより、ディズニーの個人筆頭株主となり、同社の役員に就任したが、ディズニーからの役員報酬は辞退していた。
2011年10月5日、アップルはジョブズが死去したと発表した。別の報道では死因は膵癌と報道している。享年57(満56歳)。
モノづくりにこだわり打いた生き方
有名な話がある。
ある部下が、スティーブ・ジョブズ氏から、日曜日に突然電話がかかってきました。ジョブズ氏が何かに怒り、電話をするのは平日ならお馴染みのことだったのですが、日曜にまで電話がかかってくるなんてことは、普通じゃありえなかったそうです。
当然、ビクビクしながら電話をとようですが、ジョブズ氏の電話内容はこういったものでした。
「iPhoneでGoogleのロゴを見ているのだけど、アイコンが気に食わない。Googleのロゴの二つ目のOの黄色のグラデーションがおかしいんだ。とにかく間違っていて、明日修正してくれるかな?」
という内容だったようです。
これだけ大企業のトップが、色のグラデーションまで気を使う、そのことに驚きました。
その話を聞いてから、ジョブズのファンに、本を読みあさりました。
彼はモノづくりにこだわり、徹底してスタイリッシュでクールであり続けることに
こだわったのです。
背面のデザインについての、この名言も彼の生き様を物語っています。
「もし君が家具のデザイナーでとても美しい箪笥を作っていたら、背面で誰も見ないからと言って後ろにベニヤ板をはったりするだろうか。背面でもそこに存在すると感じれば、後ろにも美しい木材を使うだろう。それは、夜よく眠るために、本物の証のために、品質のために。全てが一貫された出来映えのために、きっとそうするだろう。」
儲けじゃない、世界を変えるんだ!という情熱
最前線で働く彼らにさえ、厳しい問題がたくさんあって、簡単には解決できません。苦しんで苦しんで精一杯やる。自分を信じてとにかくやる。ジョブズ氏と共通しているのは、
お金じゃない、儲けじゃない、世界を変えるんだ!という情熱から生まれるイノベーションです。
大きなビジョンがあるからこそ、全力で走り抜けることが出来る。全力だから、細部にもこだわる。一度きりの人生、そうありたいと強く思わされました。
そして彼は本当に世界を変えてしまったのです。
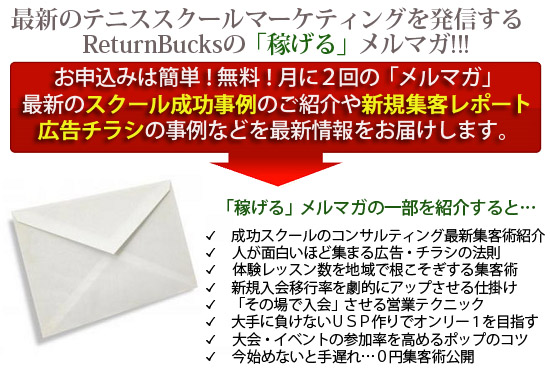
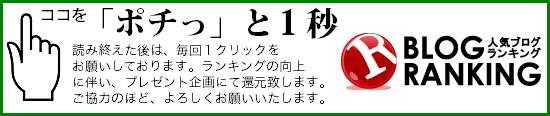

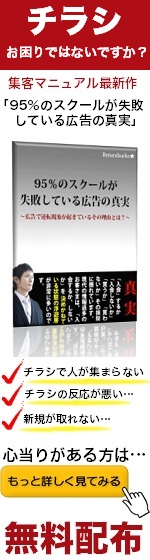
 スマホ向けのアイコンできました。
ホーム画面登録が可能です↓
スマホ向けのアイコンできました。
ホーム画面登録が可能です↓

 近日公開予定
近日公開予定










