2011年07月11日
■テニスコーチがおこす解釈とは?
今週末の2日間はコンサルティングで関西地区のスクールに行ってきました。
毎月行っているのですが、先月出たアイディアの中で、アンケートを取るという案件について話をしてきました。
テニススクールは集客のツールとして、また顧客満足度を高めるために様々なイベントを打ちます。イベントの形態は様々ですが、短期教室、試合や大会、クリニックなどスクールの個性が発揮される場面でもあります。
そのイベントはどのような目的で開催されますか?
どういったGOALが参加者さんや運営側にあるのでしょうか?
私の経験則からいうと、多くのスクールで打たれるイベントの目的が非常に「曖昧」です。
目的が「曖昧」だと、当然得られる結果も「曖昧」に終わります。
多くのイベント目的で聞かれるのが「顧客満足度」の向上という曖昧な答え。それなら「売上げの補てん」というはっきりした目的のほうがよっぽど集客率や利益率はあがります。
当然、お客さんへは最高のサービスは提供しますが。
逆に「顧客満足度の向上」でもいいのです。問題は「顧客満足度の向上?…」と“ ? ”と“…”がつくことが問題です。
仮に、「そのイベントで本当にお客さんが喜んでくれるの?」満足していただき、その満足度が継続率に反映してるの? と言われると、「?」がつくことでは、イベントの価値は半減します。
ではなぜ、イベント企画立案者が心から「顧客満足のため」と言い切れないのか?
それは多くの場合その企画が「コーチの解釈」である場合がほとんどだからです。
「本音」と「解釈」は違います。
過半数以上のお客さんが本当に望んでいる「サービス」を提供するのが本当の顧客満足度が高い「イベント」です。コーチがなにかを企画しなさい、と上司に言われて、コーチの解釈によって進めていくイベントは、「自己満足」なものになっていく危険があります。
そこで、そのイベントが「生徒さんの本音(ニーズ)」か、もしくは「コーチの解釈」であるのかを探るために、アンケートほど有効的な手段はありません。
コーチが複数集まって企画会議をするよりも、ずっと効率的で生徒さんの「リアルなニーズ」に近いはずです。
「解釈によるイベント」を乱立するよりも、本当に生徒さんが喜んでくれる真心のこもったイベントを、数回打つ方が、よっぽど顧客満足度は高まります。
「解釈による非効率なイベント」を避けるために、やはりアンケートを日常的に取り入れ、「生徒さんの本音」を聞き出してみてはいかがでしょうか?
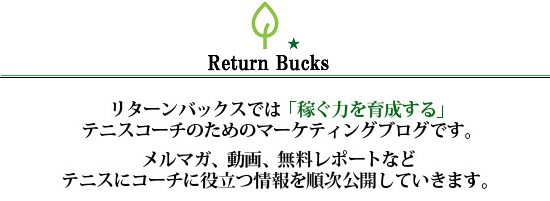
毎月行っているのですが、先月出たアイディアの中で、アンケートを取るという案件について話をしてきました。
テニススクールは集客のツールとして、また顧客満足度を高めるために様々なイベントを打ちます。イベントの形態は様々ですが、短期教室、試合や大会、クリニックなどスクールの個性が発揮される場面でもあります。
そのイベントはどのような目的で開催されますか?
どういったGOALが参加者さんや運営側にあるのでしょうか?
私の経験則からいうと、多くのスクールで打たれるイベントの目的が非常に「曖昧」です。
目的が「曖昧」だと、当然得られる結果も「曖昧」に終わります。
多くのイベント目的で聞かれるのが「顧客満足度」の向上という曖昧な答え。それなら「売上げの補てん」というはっきりした目的のほうがよっぽど集客率や利益率はあがります。
当然、お客さんへは最高のサービスは提供しますが。
逆に「顧客満足度の向上」でもいいのです。問題は「顧客満足度の向上?…」と“ ? ”と“…”がつくことが問題です。
仮に、「そのイベントで本当にお客さんが喜んでくれるの?」満足していただき、その満足度が継続率に反映してるの? と言われると、「?」がつくことでは、イベントの価値は半減します。
ではなぜ、イベント企画立案者が心から「顧客満足のため」と言い切れないのか?
それは多くの場合その企画が「コーチの解釈」である場合がほとんどだからです。
「本音」と「解釈」は違います。
過半数以上のお客さんが本当に望んでいる「サービス」を提供するのが本当の顧客満足度が高い「イベント」です。コーチがなにかを企画しなさい、と上司に言われて、コーチの解釈によって進めていくイベントは、「自己満足」なものになっていく危険があります。
そこで、そのイベントが「生徒さんの本音(ニーズ)」か、もしくは「コーチの解釈」であるのかを探るために、アンケートほど有効的な手段はありません。
コーチが複数集まって企画会議をするよりも、ずっと効率的で生徒さんの「リアルなニーズ」に近いはずです。
「解釈によるイベント」を乱立するよりも、本当に生徒さんが喜んでくれる真心のこもったイベントを、数回打つ方が、よっぽど顧客満足度は高まります。
「解釈による非効率なイベント」を避けるために、やはりアンケートを日常的に取り入れ、「生徒さんの本音」を聞き出してみてはいかがでしょうか?
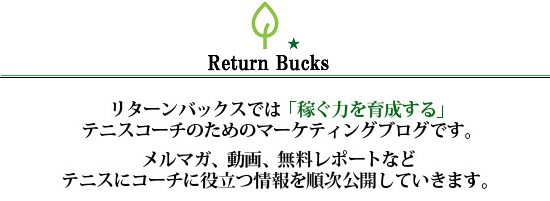
コメント
この記事へのコメントはありません。

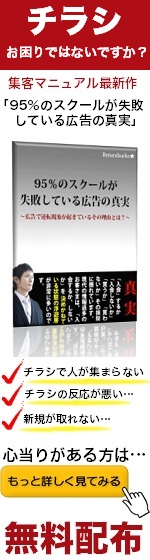
 スマホ向けのアイコンできました。
ホーム画面登録が可能です↓
スマホ向けのアイコンできました。
ホーム画面登録が可能です↓

 近日公開予定
近日公開予定










